日本のラベンダー発祥は札幌市
公開日:
:
各地の発祥の地
富良野地方におけるラベンダー発祥の地は上富良野町東中地区であること、町内の日の出公園に石碑はあるがその場所自体は発祥の地ではないこと、中富良野町の富田さんは「観光」における発祥の地といえることは以前お伝えしていました。発祥の地を語るときは意識して「富良野地方の」ということを強調してきましたが、では「日本の」ラベンダー発祥の地はどこか、ということはまだ取り上げていませんでした。今回はこの辺を探ってみます。
日本のラベンダー史にはひとつの定説が存在します。1937年、曽田香料(株)の創始者がフランスから種を持ち帰り、試験栽培の結果北海道が適地とわかり、39年札幌工場に、その後札幌市郊外南ノ沢と岩内郡発足村(現・共和町)で商業栽培がはじまったというもの。
上富良野町での契約栽培が始まったのは戦後の48年ですし、富田さんは58年ですから札幌が国内におけるラベンダー発祥の地である、と断言していいようです。
南ノ沢農場があった札幌市南区南沢地区では、東海大学札幌キャンパスが中心となって町おこしの一環としてラベンダーの栽培に取り組んでいます。

郊外の住宅街にある東海大学札幌キャンパス。早咲き、遅咲きは富良野から「里帰り」しました。

南沢神社境内にある記念碑。以下碑文。
ラベンダーの原産は南フランスで、昭和12年曽田政治氏がその種子を入手し、3年間の試験栽培の後、昭和15年に南ノ沢農場を開設して、日本で初めて香料原料として本格的にラベンダーの苗を栽培しはじめた。
最盛期の昭和30年代には、紫の絨毯を敷いたかのような美しい風景が広がり、その素晴らしさは今でも語り継がれている。
この貴重な事実を顕彰し、ラベンダーを南沢のまちづくりの象徴とするため、ここにその由来を標す。
ところで、この南沢地区と同時期に農場が開設されたのが現在の共和町。残念なことに南ノ沢農場より開設が1年遅かったために、発祥の地を名乗るには無理があるようです。それでも富良野地方より歴史はあるわけで、ラベンダーで町おこしをしてもよさそうですがまったく関心はないようです。
もう1ヵ所気になるのが曽田香料札幌工場。どうやら札幌市西区琴似地区にあったようです。となると同じ札幌でも南沢より1年早い、こちらが発祥の地といえそうです。
新事実。日本のラベンダー発祥の地は札幌市ではあるが、南沢地区ではなく琴似地区。
と(上富良野町民が)勝手に決めるものではありませんね。琴似地区の住民がそのような主張をしているわけではありませんし、日本におけるラベンダー発祥の地は札幌である、という事実には変わりありませんから。
おそらく札幌工場では一部で栽培実験や苗の供給を担っていたために「一面の紫色の絨毯」という光景はなかっただろうと想像します。だから「工場」を名乗っていたのかもしれません。試験栽培を行った北見、千葉、倉敷の各試験場が発祥の地を名乗るに値しないと一般には考えられるのと同様に、琴似地区が発祥の地を名乗るのには無理があるでしょう。
東海大学のラベンダーキャンパス化の努力によって、日本のラベンダー発祥の地が富良野ではなく札幌であることは今では広く認知されるようになりました。これからも札幌を代表するラベンダー園として維持・発展されることを願っています。
- 2010年1月25日 1年目の観覧車
- 2009年1月20日 09年本サイトが目指すもの
関連記事
-
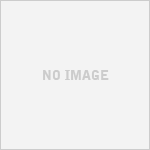
-
BS-hiの「素敵な日本」教育でも放送
早いもので今日から9月です。お盆を過ぎてぐっと朝晩は冷え込んで秋らしい気候となってきました。全国的に
-
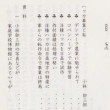
-
北の峰ラベンダー園看板の謎・中
唯一の手がかりである小林卯三郎氏の寄稿文をお送りいただけたことで、謎が解明されるかもしれません。その
-

-
富良野市史に驚愕の記述
ラベンダーの発祥の地に関して記載を重ねてきました。これまでの要点をまとめますと 上富良野町東中地区(
-

-
富田さんはラベンダー「観光」発祥の地
富良野地方のラベンダー発祥の地は上富良野町東中(ひがしなか)地区であり、その記念碑が東8線北20号に


Comment
SAKURAさま、貴重なご意見ありがとうございます!
曽田香料札幌工場に関する詳細な情報、本当にありがとうございます。日本の発祥の地を自認する南沢地区に配慮した記述となりましたが、琴似地区が本当の発祥の地ではないか、というのが私の個人的見解でした。
ただ得られる情報が乏しく、琴似地区が発祥の地を名乗らない理屈を考えてみたわけですが、見事に論破していただけて、やはり琴似地区が発祥の地を名乗るにふさわしいだろうという思いを持ちました。
私も発祥の地を競うこと自体、意味のないことだと思います。誤った情報も氾濫する中、今日に至る日本ラベンダー史の本当の姿に近づきたいだけです。
SAKURAさま、貴重なご意見重ねてありがとうございました。また何か情報お持ちでしたらよろしくお願いします。
さきほどのコメントの最後の一文、失礼な言い方になってしまったかもしれません。
気を悪くされましたら、申し訳ございません。
「どれが発祥地かを論じるよりも」ではなくて、
「どれが発祥地かを競うよりも」と言うつもりでした。
訂正して読んでいただければと思います。
ラベンダーの発祥地について、ひとこと。いえ、ふたこと、みこと…もっと?(笑)、よろしいでしょうか。
「札幌工場では一部で栽培実験や苗の供給を担っていたために『一面の紫色の絨毯』という光景はなかっただろうと想像します。だから『工場』を名乗っていたのかもしれません。試験栽培を行った北見、千葉、倉敷の各試験場が発祥の地を名乗るに値しないと一般には考えられるのと同様に、琴似地区が発祥の地を名乗るのには無理があるでしょう。」との記述について。
札幌の琴似地区にあった曽田香料札幌工場は、ハマナスの香料を抽出するために設けられた工場です。バラの原種のひとつであるハマナスからは、ローズオイルに匹敵する高級香料が採れたんです。花びらのデリケートな香りを保つには、高熱を加える水蒸気蒸留は不向きなので、ハマナスオイルは溶剤抽出法という手法によって生産されていました。「工場」と呼ばれたのは、溶剤抽出装置を備えていたためです。
日本初の本格的なラベンダー栽培地を言うなら、昭和14年にこの工場の裏につくられたラベンダー畑(曽田香料札幌工場付属農園といいます)ということになります。広さは0.5ヘクタールほどでしたので、南沢農場や岩内農場に比べると規模は小さいですが、工場が閉鎖する昭和43年まで大切に栽培され続けました。毎年、刈り取りも行われ、当時は希少であった溶剤抽出によるラベンダーオイル(ラベンダー・アブソリュート)の原料となっていたんですよ。
北見や千葉、倉敷らの試験栽培地が発祥地とされないのは、それが生育に適した地であるかどうかを調べるための一時的な試験であったからにすぎません。南沢農場や岩内農場と同様に、30年もにわたり栽培され続けた生産農場であった琴似のラベンダー畑を、これら試験栽培地と同列に扱うことはできません。また、生産性を上げるためのさまざまな研究試験が行われたり、挿し芽で育苗をして栽培農家に苗を供給したのは、南沢農場や岩内農場も同じです。
札幌工場付属農園でも、毎夏、一面をおおうラベンダーが花を咲かせていたんですよ。発祥地を名乗るのに無理があるのではなく、ここが発祥地だと声を上げる人がいなかっただけのことなのです。そのうちに、ここにラベンダー畑があったことを知る人が少なくなってしまったというのが現実です。しかしながら、この間、札幌工場に勤務した曽田香料の関係者など、ここが発祥地であることを知る者は、複数、健在しています。
発祥地は、言ったもの勝ちみたいなところがありますからね。正確にいえば、栽培の発祥地が琴似(札幌)、蒸留の発祥地が南沢(札幌)と岩内(共和町)です。
どれが発祥地かを論じるよりも、正しい歴史を伝え残していくのが、大切ですね。