今年(06年)のラベンダーは薄かったか
公開日:
:
ラベンダー豆知識
例年なら10月下旬には初雪があるのですが今年はまだのようです。ラベンダーの生長もストップし、あとひと月もすると雪がすっぽりラベンダーを覆い、保温材となって富良野の厳しいシバレから守ってくれることでしょう。
タイトルのネタ元は9月2日付道新ふらの面の署名記事「今年のラベンダー 色薄かった?」から来ています。ふらの面ですので道内でも富良野地区の読者しか記事は目にしていないと思いますが、ずっとこの記事のことがひっかかっていたので取り上げてみます。
記事の内容は『今年は富良野地方を訪れた人から「ラベンダーの色が薄い」という声が聞かれた』ということでその原因を探っています。
日の出公園ラベンダー園を管理する振興公社常務は昨年11月の大雪を挙げ『ラベンダーが突然の寒さに準備できていなかった』ことが原因で多くの株が枯れたため『花の穂自体の色は例年通りの濃さだったが、全体的には薄く見えた』と説明しています。
ファーム富田社長は『春先の低温で雪融けが遅かったことも要因の一つ』とし、ファーム富田でも二千株以上のラベンダーが枯れて補植したのだそうです。
さて、私の個人的な見解です。
我が家には数百株のラベンダーがありますが、事実この春は例年以上に枯れた株が多くありました。当初は私の管理の仕方が悪かったのだとへこんでいたわけですが、後にあちこちのラベンダー園で枯れが目立ったので私のせいではないと少し安心したものでした。
その原因については思い当たるものがなかったのですが、記事によって振興公社の「昨秋の寒さ」説とファーム富田の「今春の低温」説が挙げられました。
しかしこの両方の説とも、実は私は納得していません。
「昨秋の寒さ」説に関していえば具体的にいつのことだったのか、そんな寒い日があったのかピンと来ないのです。例えば3日くらい前に氷点下5℃になりましたが、このくらいの寒さで枯れていたら、毎年同じくらい枯れることになるでしょう。
「今春の低温」説についても去年だって同じくらい雪融けが遅く見頃の時期も遅れたことを考えると、素直に首を縦には振りにくいのです。大雪山系では斜面によって雪融けの時期は何十日も違いますが、融けたところから順次高山植物が開花するように、雪融けの早い遅いでラベンダーは枯れたりしないと思うのですが。
この件に関して、おもしろい花の付き方をしたのが中富良野町の彩香の里・佐々木ファーム。8月11日の最新リポートで『茎の数が少ないのを心配していましたが、今頃になって花を付け出しているという印象』と書きましたが、オーナーさんに伺ったところ「雪融け直後は青々していたが、その後の低温で枯れる株が出た」ということでした。『遅効性の肥料を用いた』という印象でしたがそうではなく、本来一斉に伸び始めるラベンダーの新芽が、春の低温によっていったん抑えられ、ずれる形で伸びだしたことで、後から咲き出したという見解でした。この意味ではタイトルどおり「ラベンダーは薄かった」といえます。
一方8月4日のリポートで『まったく雨が降らなかったことで、1つは早く咲いた花びらが枯れずに残りボリュームが出たこと、もう1つは陽射しを浴びる時間が長かったことによって花びら自体の青紫色が濃くなった』と指摘しました。つまりここでは「今年のラベンダーは濃かった」と表現しています。
以上をまとめると今年のラベンダーは
枯れたラベンダーが多かったことで全体的には薄く見えた(ところもあった)。
雨が降らない日が続いたことで一つ一つの花は濃くなった(時期もあった)。
ということになるでしょう。
ただ枯れた「本当の原因」は今もって私は納得していませんが。
- 2010年1月25日 1年目の観覧車
- 2009年1月20日 09年本サイトが目指すもの
関連記事
-

-
すくすくと成長していないラベンダーオーナー園
ここ数日は北海道の夏らしい、カラッとした暑さが続いています。今日は富良野市で今年初の真夏日を記録しま
-
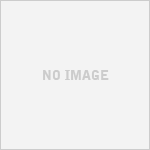
-
満開=見ごろではないラベンダー
ラベンダーの見頃の状態を表現するのに、各市町では見頃指数を10段階評価で表し「○分咲き」という表現用
-
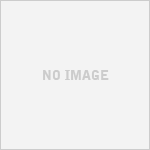
-
見ごろ差の要因は標高差
今年(2010年)を振り返ってみますと、春先の天候不順で遅れがあり、大冷害との予測もあってヤキモキし
-
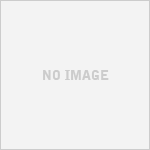
-
ラベンダーは多年草?
毎年初夏に花をつけるラベンダー。多年草と説明している本やサイトもありますが、栽培管理している立場から
-

-
枯れる被害の大きいラベンダー畑
今年は例年より3日ほど早く生育しているのは、前回データでお伝えしたとおりです。早咲きは日増しに色を付
- PREV
- ラベンダーの冬支度
- NEXT
- ラベンダーの挿し木の方法・その5(移植)
