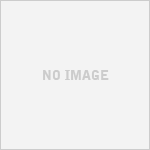室内冬越しラベンダー
公開日:
:
管理作業
今年は暖冬で積雪は少ないとはいえ、富良野のラベンダー畑はまだどこも雪に覆われています。それでも確実に春の足音は近づいており、あと10日もすればラベンダーは雪の中から顔を出すことでしょう。
冬の間はラベンダーに関してはすっかりネタ切れ、社会派? な記事ばかりエントリーしていましたが、今回は久しぶりにラベンダーネタ、室内で冬越ししたラベンダーの近況報告です。
以前の記事「ラベンダーの冬支度」で取り上げましたが、雪の中に埋めてしまうのが楽な冬越しの方法ですが、それができない場合は室内での冬越しということになります。
今年も5株ほど室内での冬越しを行いました。昨年同様暑いときは30℃、夜にストーブが消えると0℃前後という外にも増してラベンダーには厳しい? 環境の中、3月の中旬頃から新芽が伸び始めました。
11月以降まったく変化のなかったラベンダーが、何をきっかけに新芽を伸ばし出すのか不思議なのですが、考えられることの1つは日長(夜明けから日没までの時間の長さ)です。長日条件(徐々に日が長くなること)がラベンダーの生育に何らかの影響を与えていることが考えられます。冬季も温室でラベンダーを咲かせるファーム富田で夜間照明を実施しているのはこの辺と関係がありそうです。
もう1つ考えられるのは、休眠打破です。桜の花芽などがそうですが、冬期のある一定期間低温にさらされてはじめて芽が出る性質を備えています。ラベンダーの種を蒔くときに催芽処理(この場合は冷蔵または冷凍すること)をした方が発芽率が上がるという性質から、ラベンダーにもそのような性質が備わっていると考えられます。
さて、せっかく伸びてきた新芽ですが、薄暗い室内でまだ弱い日光しか浴びられないままだと昨年と同じ失敗を繰り返すでしょう。

軟弱に育った昨年のラベンダー。
真っ直ぐ育てるためには鉢をグルグルまわすという方法があるのですが、面倒くさいというのが正直なところ。そこで今回はラベンダーに白い紙と銀紙(アルミ箔)をそれぞれ巻いて、何とか光を集めて真っ直ぐに生長させる努力をしてみます。

失敗してもカットすれば夏までにはもう一度花をつけます。その頃には気温も上がり外で管理できるので、陽の光をたっぷり浴びて元気に育つことでしょう。
- 2010年1月25日 1年目の観覧車
- 2009年1月20日 09年本サイトが目指すもの
関連記事
-

-
<図解付き>ラベンダーの剪定位置
これまで当ブログではラベンダーの刈り込みは絶対にしなさいよ、と口が酸っぱくなるほど強調してきました。
-

-
剪定した株としない株
剪定に関する質問をいくつかいただきましたので、剪定した株としなかった株を見比べることでどのような違い
-

-
ラベンダーの刈り取りは必須事項
例年お盆前後にはすべてのラベンダー園でラベンダーの刈り取りが行われています。基本的には「でめんさん」
-

-
切断面でわかる枯れ具合
富良野では肌寒い日が続いています。春は三寒四温で暖かくなっていくものですが、感覚的には五寒二温くらい
- PREV
- 富良野に道の駅は必要か
- NEXT
- 「富良野道路」は本当に必要か(下)