脱原発目指す田舎暮らし
公開日:
:
その他
タイトルを少し柔らかく変えました。前回はライフラインを中心に今の暮らしを紹介しましたが、今回は目指す田舎暮らしの方向性について書いていきます。改めてお断りしておきますが、自分の考えをまとめきれていないのでその辺は差し引いてお読みください。
一言で田舎といっても千差万別で、百人いれば百通りの田舎暮らしがあります。田舎暮らしの定義はいろいろありますが、ここでは自給的、自立的な暮らしを指すことにします。したがって田舎に住んでいてもアパートでコンビニ通いのような人は田舎暮らしではありませんし、逆に自立的な田舎暮らしを実践する都市生活者も大勢います。
前回は私なりの田舎暮らしの一端を紹介させていただきました。自給的、自立的な暮らしは今では一つの思想といえますが、実のところ何のことはない、ちょっと昔の普通の暮らしで、それに現代的な味付けがされただけです。
このちょっと昔というのをどの辺を指すか私の中で曖昧なままでしたが、今回の福島原発の事故を受けはっきりしました。調べてみると日本で原発が稼動を始めたのは昭和38年のこと。反原発思想もとい脱原発を目指すのなら、昭和30年代の暮らしを取り戻すことに活路を見出せるのではないかと思い至りました。
都会暮らしの便利さを享受しながら、原発には反対し、電力不足を嘆き、景気回復を唱えることは二重三重に矛盾しています。現代の豊かさや便利さと原発とを天秤にかけ、それでも原発を支持するなら私には言葉はありません。
もし心の底から原発は要らないと確信するのであれば、物質的な豊かさは捨てなくてはなりませんし、景気の動向に左右されない生き方を目指す必要があります。そしてその生き方を実践できる場が田舎にはあるのだろうと思います。
ちょっと話しが逸れますが仙台での学生時代、世間では過激と思われている人たちと一時期行動をともにしました。さまざまなテーマがありましたがそのスローガンのほとんどが「○○反対」という他者(主に権力者でしたが)への働きかけでした。
六ヶ所村や女川にも出かけて「原発反対」を叫びましたが、では翻って電気を無節操に使って恥じない自分の暮らしぶりを反省する姿勢は皆無でした。例えていうならオレンジの輸入自由化反対と叫びながら、喉が渇いたので濃縮還元ジュースを飲むようなものです。
他人は変えられないけど自分は変えられる。そんな思いも私の田舎暮らしの決意を後押ししたのかもしれません。富良野に移り住んで十余年。現在地に土地と住まいを求めて7年ほど経ちます。それまでの価値観を捨て、ときには思い悩み立ち止まったこともありますが、とりあえず目指す方向性は間違っていないであろうことは、今回の震災が教えてくれたような気がします。
現在日本の「繁栄」は過去の遺産(石油エネルギー等)を食い潰し、未来へツケ(環境破壊等)をまわすことで成り立っています。原発に反対すると同時にエネルギーの消費を少なくすること、身の丈に合わせて小さく生きることが一つの解決策だと考えます。
3・11から私たちは何を学ぶのか。子供たちに夢と希望に満ちた、誇りの持てる日本を引き渡すにはどうしたらいいか。日本人一人一人の生き方・暮らし方が問われていると思います。
最後にもう一度お断りしておきますが、頭の中でまとめきれないまま書きました。後で修正するかもしれません。また論戦を挑むようなコメントはご免被ります。
- 2010年1月25日 1年目の観覧車
- 2009年1月20日 09年本サイトが目指すもの
関連記事
-
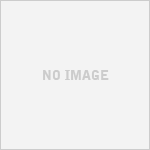
-
勝手に富良野安全宣言
今年のゴールデンウイークの曜日配列から、今日はエアポケットのような平日となっています。好天に恵まれた
-
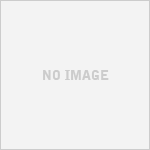
-
田舎暮らしの災害対応力
大震災から一月が経過しました。心の中の時計の針は今も止まったままです。安否のわからない方が今なお1万
- PREV
- 田舎暮らしの災害対応力
- NEXT
- 切断面でわかる枯れ具合
